今回の配布で、網戸作成スペックは、4回目となります。
今まで、材料調達・木取り・木取りした材の加工までを、ご説明しました。
今回は、いよいよ、組立(組立の手順)となります。
木材が、作品になって行く組立の工程が、一番、楽しい時間です。
ただ、可動する作品なので、この工程が、一番、苦労するかもしれません。
苦労した分だけ、完成した時の喜びはそれ以上なので、頑張って下さい。
その前に・・
今回の0513窓用上げ下げ網戸は、網の張り替え時まで考慮に入れています。
組立前に、もう一手間掛けておきましょう。
この工程は、中上級者の方にお薦めします。
初級者の方でも、網の張り替えを簡単にしたいとお考えの方は、追加工して下さい。
■網の固定方法
以前、網を固定するために、タッカー(ホッチキスの親分)で、内枠の裏側に、止めまくるとお話しました。
1枚の網を内枠に固定するのには、50カ所ほどタッカーを打ち付ける必要があります。
これでも、網は固定出来ますが、張り替え時は、とても大変です。
一度、間違えて打ったタッカーを外してみられると分かりますが、
本当にしっかり打ち込まれていて、なかなか抜けません(^^;)
これが・・50カ所以上、抜くとなると・・
考えて見るだけでも、うんざりです。
あと、タッカーで網を固定しているので、厳密に言うと沢山の点で網を押さえて
いることになり、網も点で負荷が掛かり、やぶれやすくなっています。
今回の改良版は、網を面で固定する方法です。
具体的には、アルミ板材(1mm厚10mm幅)の物を使用して、板(面)で、
網を押さえつける事によって、網の負荷を極力さけて、張り替え時には、
アルミ板をはずすだけで、網の交換が出来るようにすると言う構造です。
では、アルミ板の加工の説明です。
アルミ板材は、ホームセンターなら、どこでも手に入ります。
1mの長さで購入出来ますので、5〜6本用意します。
材料取りは、内枠の縦・横に合わせて、切断します。
サイズは、やはり横通しとしますので、縦材を622.5から−80した寸法の542.5mmを4本、横材として325mmに+20した345mmを4本、クリアランス(隙間)として、−2〜3mm見込みますので、縦材は540.5〜 539.5mmで、切断して下さい。
切断には、ペンチ・金ノコなどの工具が必要です。
さて、どうして今回は、横通しで材料取りをするのでしょう?
答えは・・
組上がりを考えると分かるのですが、内枠は縦通しで組立られます。
枠の固定(組立)は、横材からコーススレッドを1本打ち込んであるだけです。
これでは、固定枠は問題ありませんが、可動内枠が、ちょっと強度が心配です。
それで、アルミ板を網を固定するだけの役目ではなく、枠の強度も上げる役目を持たせるために、わざわざ横通しとしているのです。
折角、完成した網戸が、上げ下げしたらバラバラになったでは、洒落になりません(^^;)
こんなちょっとしたアイデアが、自作の良い所です。
アルミ材は、部材としては高価(1本600円くらい)なので、よくサイズを確かめてから切断して下さい。
次に切断したアルミ板に、ビス止め用の穴を開けていきます。
穴径は、鉄工用錐(2.7mm)を使用します。
2本入って300円くらいで購入出来ます。
ビスは、出来ればステンレス製タッピングビスを使用します。
縦材には、12カ所、横材には、8カ所ほど穴を開けます。
縦材は、542.5mmを等間隔に割って行き、穴を開ければOKです。
横材は、内枠を固定する意味もありますので、まず、両端に穴をぎりぎりに開けます。
そこから、20mmピッチで、穴を開けます。
あとは、縦材と同じく等間隔に穴を開けて行きます。
多少、中心を逸れたり、間隔が均等でなくてもかまいません。
穴あけのポイントは、横材で内枠を固定出来るように穴あけ位置を決める事です。
穴を開けたら、裏側にバリが出ますので、鉄工錐4mmで、皿を揉んでおきます。
バリを取るためと、固定用皿ビスの頭を埋没させるためです。
固定用のビスは、太さ2.5mm 長さ16mmの皿ビスを穴を開けた分、使用します。
■ちょっと一息(^o^)
第1回で、可動枠を固定する為の金物として、雪見障子用の板バネを紹介しました。
ただ、どこでも手に入ると言うものではないので、入手するのが困難です。
そうしました所、いのさんから、耳より情報を頂きました。
WebShop 新井建具製作所さんで、1個から板バネが購入出来ます。
http://www.mis.janis.or.jp/~joiner/order1/frame.html
1個の値段も非常にお値打ちでなので、板バネをご使用になるご予定の方は、
こちらでご注文なさると良いと思います。
いのさん、良い情報をありがとうございました。
■いよいよ組立て
では、本題の組立の説明です。
組立は、今回(組立の手順)と次回(組立と調整)の2回に分けます。
部材は、すべて揃った状態で、組立作業を始めます。
材料が揃ったので、すぐに組み立てたくなるのは、誰でも一緒です(笑)
ここは、はやる気持ちをぐっと抑えて、組立手順を考えて行きましょう。
まず、今回の網戸は、大きく3つの部材に分かれていると説明しました。
外枠・固定内枠・可動内枠です。
まず、外枠をコーススレッドで、仮組して、実際に使用する窓にはめてみて、ちゃんと窓枠に収まるか確認します。
これが収まらないと、いきなり内枠を組立て、組み込んでも、あとから全部、バラしてやり直しになってしまいますので、必ず、実物合わせして下さい。
外枠が、ちゃんと窓枠に収まったら、いよいよ、内枠作りです。
外枠と同じように、固定内枠から仮組してみます。
仮組が出来たら、外枠に収めてみて、確認して見て下さい。
同じ、要領で、可動内枠も仮組して、外枠に収めてみます。
この状態では、まだ、可動用のレールがないため、可動するかの確認は出来ません。
あくまでも、計算通りに、外枠に無理なく収まるかの確認です。
収まることが確認できたら、もう一度、すべてバラします。
次に、可動内枠が可動出来るようにする作業です。
この工程(組立)は、次回の説明に回します。
この後、外枠を一番下になる横材を除いて、組み立てます。
次に、内枠を組み立ててから、網張り作業となります。
各部分の組立が、それぞれ終わったら、すべてを合体させます。
以上のような手順が、組立工程です。
チャートでしめすと・・
外枠仮組(確認)−固定内枠仮組(確認)−可動内枠仮組(確認)−可動させる工程
−外枠本組立−固定内枠本組立−可動内枠本組立−すべてを合体−調整−完成(^o^)
今回のポイントは、仮組立てです。
どんな物を作られる場合でも、必ず、仮に組み立てて問題が起きないか確認することが、非常に重要です。
行き会ったりばったり(僕?(爆))でも、奇跡的に上手く行くことはありますが、後から、しまった!(涙)と言う事の方が、圧倒的に多いです。
特に、可動する物・大物・mm単位の精度を要求する物など、後から、追加工が出来ない場合もありますので、面倒くさがらずに一手間掛けて下さい。
中上級者の方は、よく分かっていらっしゃる事ですが、
一手間掛ける事が、作品の精度・強度・外観(作品の完成度)を、格段に上げる事が出来ます。
特に可動する作品は、机上の計算通りに行きません。
計算した通りに行かない所が、また楽しい所なんですけれど・・(笑)
今回の上げ下げ網戸も、スペック通りに木取り・加工をされたとしても、そのまま、窓枠にはめても、まず、スムーズに動きません。
スムーズに動かないどころか、まったく動かないくらいに思って下さい。
で・・
次回の組立&調整の説明が必要になります。
動かない物を動かす・動かないなら、動くようにしましょう(笑)
それでも、動かないなら、自分(素人)で作った物だから、仕方ないか〜(^^;)くらいの心の余裕を持って、取り組んで見て下さい。
プロではないので、初めて作って動かないのは当たり前です。
なんの問題もなく、動いたら、プロは必要ありません。
失敗して当たり前なんだと言う気持ちと、どこが悪かったのだろうと言う気持ちが、DIYerには、いつまでも必要なことだと思います。
次回は、いよいよ、上げ下げ網戸完成(^o^)/です。
5回にわたってお届けする、木製網戸の作り方・詳細手順です。
■■■ ミニ・目次 ■■■
■手作り木製網戸レシピ その1 準備するもの
■手作り木製網戸レシピ その2 木取りの説明(前編)
■手作り木製網戸レシピ その3 木取りの説明(後編)
■手作り木製網戸レシピ その4 組み立て手順(前編)
■手作り木製網戸レシピ その5 組み立て手順(後編)
以下、ワタクシあすきっとが2005年夏に網戸を作った記録
■手作り木製網戸 その1
■手作り木製網戸 その2
■手作り木製網戸 その3
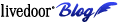
 カンタン!ブログをはじめよう
カンタン!ブログをはじめよう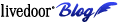
 カンタン!ブログをはじめよう
カンタン!ブログをはじめよう
